フランスパリにはアートの名所がたくさんありますので、パリ旅行の観光に美術館訪問はいれたいですね。
パリの美術館と言えば、ルーブル美術館やオルセー美術館、ポンピドーセンターなどが有名です。
一方、パリには、著名な芸術家の住居やアトリエがそのまま美術館になったところが多いのでもし気になる芸術家がいたら抑えておくといいです。
今回ご紹介する「モロー美術館」もそのひとつになります。
モロー美術館
19世紀の前半から後半にかけて芸術家や文化人が多く住んだのは現在のパリ9区です。
オペラ座やギャラリー・ラファイエット百貨店から北側の高台だったのです。
19世紀前半から後半のパリはここ「サン=ジョルジュ」地区に芸術家村と呼べるような雰囲気がありました。
「サン=ジョルジュ」地区にショパンや女流作家の先駆けになったジョルジュ・サンドがいました。
画家であれば、ドラクロワなど。
ここには、「ロマン派」のアーティストたちでアートや音楽、文学の潮流で、個々の感情や異国への憧れ、恋愛や憂鬱、不安などを自由に表現しようという運動。
本格的に個人主義が文化の主流になり始めた時代ともいえるかもしれません。
そんなロマン派に影響を受けて育ちながら、独自の作風を創りあげていったのが、ギュスターヴ・モローでした。
パリ9区ラ・ロシュフーコー通りにある屋敷は、ギュスターヴ・モローが亡くなるまで住んでいました。
それが、モロー美術館です。
彼は亡くなる前から、この屋敷を国に遺すための準備を始めたといいます。
彼の友人や弟子の手を借りながら、作品を選択していたと言われています。
国立美術館として、彼の暮らしぶりも含めて、油彩や水彩、素描とともに、公開されています。
独特の絵を描いていたギュスターヴ・モローの作品が観たくて旅行で美術館を訪ねました。
個人の家が美術館として公開されているのも初めてでした。
美術館の中に足を踏み入れると、壁や家具の色彩が統一されて住居自体が崇高な雰囲気を醸し出していました。
また、螺旋階段があり、階段を登りながら次の階に行くのがたいへんワクワクさせる空間でした。
ギュスタブ・モローってどんな人
1826年、パリのサン・ペール街でギュスターヴ・モローは生まれました。
父のルイ・モローは国立美術学校で学んだ建築家。
母のポーリーヌは地方地主の娘でドゥエー市長を務めたこともあるモローの理解者でした。
1歳年下に妹カミーユがいます。
モローは8歳で素描を習い始め、10歳になるとロラン中学の寄宿生になしましたが、学校になじめなかったようです。
ギュスターヴ・モローが14歳のとき妹カミーユが亡くなったのをきっかけに自宅に戻りました。
り家に戻った。翌年モローは母親や親類とイタリア各地を旅し、素描を残した。
1844年18歳でバカロレア(大学入学資格)を取得しました。
画家になることが父親に認められて、1846年国立美術学校に合格しました。
ローマ賞コンクールへ何度か参加しましたが、落選が続いたため、国立美術学校を退学しました。
ドラクロワなどの影響を受けながら、独学で描き続けました。
1852年、官展サロンへ出品したピエタという作品が初入選しました。
続いて、1855年にはパリ万国博覧会に出品しました。
その後、1857年、私費でイタリアを旅行し、1年間、昼はルネサンス期の名画の模写、夜はデッサンに取り組みました。
1864年から1869年までサロンへ作品を出品し続けていきます。
作品も独自のテーマ性があって、皇帝ナポレオン3世の目に止まり、お城に滞在することも許されます。
独自のテーマとは、聖書や神話となりました。
そして、1866年のサロン出品作オルフェイスが国家の買い上げとなり、翌年のパリ万国博覧会にオルフェウスなどを含む3作品が出品されました。
1869年にサロンの出品で3回目の褒章メダルを手にした後には、無審査でサロンへ出品できるようになっていきました。
1870年、普仏戦争に志願しますが、リウマチによって除隊となりました。
1875年にレジオン・ドヌール勲章を受章しました。
1888年、美術アカデミー会員に選出され、1891年からはエコール・デ・ボザール(国立美術学校)の教授となりました。
20世紀を代表する画家ジョルジュ・ルオーや画家アンリ・マティスらを教えました。
1892年には、官立美術学校の教授となりました。
ギュスターヴ・モローの方針は、弟子たちの個性を尊重し、その才能を伸ばすことを大切にしました。
生徒達には、「私は君たちが渡っていくための橋だ」と話していたそうです。
1898年、癌のために死去。
国立美術学校に入ったものの、出品作が落選続きのため、学校を辞めました。
ただ、独自の学びのために1年間イタリアをめぐり、昼夜問わず作品を描き続けたギュスターヴ・モロー。
その期間の結果、ピエタ、オルフェス等の作品で世に認められ、やがては審査なしで出品ができるようにまでなりました。
モローサロメ
印象派の画家たちと同時代に活動したモローですが、題材はユニークでした。
聖書やギリシャ神話をヒントに想像と幻想の世界を描いたのです。
その作品は、19世紀末の画家や文学者に影響を与えました。
そのため、象徴主義の先駆者として位置付けられています。
イタリア旅行の際は、これまでのイタリアの画家たちの作品に大いに影響を受けたようです。
ルネサンス芸術研究とアカデミーでの修行から作り上げていったモロー独特の技法です。
モローが残したメモからは彼が善と悪、男と女、物質性と精神性の二項対立を意識していたことがわかります。
サロメという作品は物語から構想を得ています。
ユダヤの王エロドは、自分の兄である前の王を殺し、その妃を奪って王の座に就きました。
妃の娘であるサロメにも魅せられ、サロメを見つめるのです。
その視線に堪えられなくなったサロメは、宴の席を離れ洗礼者ヨハネが閉じ込められている井戸に向かいます。
洗礼者ヨハネは不吉な言葉を喚き散らすため、妃から嫌がられていました。
ヨハネとの接触は王により禁じられていますが、サロメは色仕掛けで見張り番であるシリアの青年に禁を破らせることで、洗礼者ヨハネを目撃してしまったのです。
サロメは預言者ヨハネに恋をしてしまいました。
ヨハネは彼女の忌まわしい生い立ちをなじるのです。
預言者ヨハネに拒まれたサロメは、ヨハネに口づけをすると誓うのでした。
エロドはサロメにダンスをすることを要求する傍らで、何でも好きなものを褒美に取らせると約束します。
そこで、サロメは7つのヴェールの踊りを踊って、褒美として洗礼者ヨハネの首を所望するのです。
洗礼者ヨハネの力を恐れるエロドはこの要求を断ります。
しかし、あきらめないサロメに対して、エロドは洗礼者ヨハネの首をサロメにとらせます。
銀のさらにのせて運ばれてきた洗礼者ヨハネの唇にサロメは口づけをして恋を語ります。
この様子をみたエロドはサロメを殺害させるのです。
私が初めてギュスタブ・モローの作品を観たのがサロメでした。
物語は恐ろしいですが、独特の作風を観て、魅せられました。
生涯の中で、リスペクトをしあえる仲間と出会えることは幸せなことだと思います。
彼が人生を過ごしたギュスターヴ・モロー美術館をぜひ訪れてほしいと思います。
印象派とは、まったく違った作品と彼が生涯住み続けた自宅の中には、独自の世界を作り上げた種が残っているのです。

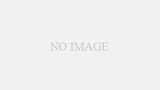
コメント