今回は、スパイスの話題を取り上げます。
最近はエスニック料理も普通に食卓にのぼる時代です。
その料理に使われているクミン、シナモン、ブラックペッパー、クローブ等はスーパーのスパイスコーナーでたくさんの種類を見かけます。
その中から、今回はカルダモンを取り上げてご紹介していきます。
「スパイスの女王」を使いこなせ!
カルダモン、スパイスとは?
植物と人はいつごろから関わってきたのでしょうか。
食用や薬用だけではなく、五感を利用して、四季ごとに植物の恩恵を受けてきました。
例えば、食品の保存や防腐のためにハーブ・スパイスが使われてきました。
古代から染色のために植物を使い、多様な色を生み出してきました。
このほかにも、祈りや儀式にも活用されてきました。
医薬品がない時代には、ハーブ・スパイスは薬草として病気の治療や予防に用いられてきました。昔から続く伝統的な自然療法は代替(だいたい)療法といいます。
自然療法が目指すところは、人が持っている自然治癒力を高めることです。
ハーブ・スパイスは形態によって、生のままをフレッシュ、乾燥したものをドライと言います。
ドライは乾燥させたハーブ・スパイスのことで長期保存が可能ですし、フレッシュよりも手に入れることが簡単にできます。
カルダモンはドライのハーブ・スパイスです。
利用する部位による分類もあります。
蕾やめしべを利用する者、ひとつの植物で複数の部位を使うものもあります。
サフランは、めしべを使いますし、バニラはバニラビーンズの果実からとります。
それでは、カルダモンについてみていきましょう。
カルダモンは「スパイスの女王」と呼ばれ、世界各地で珍重されています。
カルダモンはショウガ科に属しており、産地はインド、スリランカ、マレー半島です。
使用部位は果実になります。
果実の中に種子が入っています。インドをはじめ北欧、中東、エジプトなどで広く愛用されています。
古くから香辛料や芳香性健胃薬として珍重されてきました。
インドではカレーやガラムマサラに多用され、アーユルヴェーダでは最も安全な消化促進剤とされています。
北欧ではケーキやパンに、日本ではカレー粉の主原料にも使われます。ハーブ&ライフ検定テキスト公式テスト 特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会検定委員会 抜粋
医薬品がなかった時代にハーブ・スパイスは病気治療や予防に使われてきた歴史があります。
食品の保存や防腐にも必要だったハーブ・スパイス。
カルダモンは、世界中で珍重されてきました。
香辛料であり、健胃薬の働きもあります。
胃腸薬を使うのもいいけれど、料理や飲み物に取り入れる方法がわかれば、食べ過ぎた後に実践ができます。
もっとカルダモンと仲良くなれたらいいですね。
カルダモン、効能は?
カルダモンの効能の前に、ハーブ・スパイスの働きについ説明しておきます。
効能でいわれる働き、食べた人全員に同じように働きかけ訳ではないことを知っておいてください。
ハーブ・スパイスの一般的な働きをお伝えします。
〇老化を進める細胞の酸化をおさえる働き
〇心身の状態をバランスよく保とうと調節する
〇病原菌などから身を守ろうとするはたらき
〇炎症や痛みを和らげたり、筋肉の緊張をほぐしたりするはたらき
〇ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素を供給するはたらきこのほか、消化の機能を高めたり、気分を明るくしたり、抑うつを軽減するなど、さまざまな働きがあります。
公式テキスト ハーブ&ライフ検定テキスト NPO法人日本メディカル協会検定委員会監修 抜粋抜粋
ハーブ・スパイスに含まれる多様な成分を効率よく利用するには、性質にあったとり入れ方を選ぶのが大切です。
食べたり飲んだりして体内にいれる場合もあれば、アロマセラピーのように皮膚などから精油成分を吸収させるかなどを考えます。
味方にすれば、老化を進めることをおさえたり、病原菌から身を守ったりもできます。
その条件として、誰にでも一律に作用が働くとは限らないことも忘れずに。
それでは、カルダモンをアーユルヴェーダの視点でみていきます。
学術名:Elettaria cardamomum
サンスクリット名:ニラ
植物和名:ショウガ科しょうずく
使用部位:種
ラサ:辛味、甘味
薬力源:熱性
消化後の味:辛味
ドーシャへの作用:V↓、K↓、過剰摂取でP↑
作用:興奮・刺激作用、去痰作用、駆風作用、健胃作用、発汗作用
主な適応症:疲労、風邪、咳、気管支炎、喘息、かすれ声、消化不良、情緒不安定
主要成分:精油d‐ボルネオ―ル、d‐カンフル、1.8シネオール、α及びβ-テルピネン、α及びβピネン
基本的な使い方:浸出液(沸騰させない)、粉末(100~500㎎)、牛乳を用いた浸出液緑色のさやの中の黒い種子にすっきりさわやかな芳香があります。
刺激作用やリフレッシュ作用があり、消化の火・アグニ※を燃えたたせて、胃と肺からカパを除去します。
※アーユルヴェーダでは体や心の動きの基礎に働くエネルギーをドーシャといいます。 食物がどのように体に影響するかはドーシャのバランスによるとされています。
特にドーシャのバランスを崩すとアグニ=消化の火が不安定になります。インドの医食同源にもとづく、お手軽レシピ アーユルヴェーダカフェ 地球丸からだブックスより抜粋 地球丸
アーユルヴェーダの視点でも、カルダモンは「消化」をサポートしてくれるハーブ・スパイスだとわかりますね。
疲労回復や風邪をひきそうなときにも取り入れてみたいですね。
風邪に適応するということは、呼吸器系にもよさそうです。
もちろん医薬品ではありませんので、食事や飲み物に活用してみてもいいと思います。
会食が続いたり、集まりが続いた時には、消化の火がバランスを崩す可能性もあるため、カルダモンを思い出すしましょう。
かつて、OLをしていた頃に、残業が続き、夕食が遅かったり外食も多かったので、胃腸の調子がよくなかったです。
アーユルヴェーダの視点でいえば、ドーシャのバランスが乱れ、おそらくアグニ=消化の火が不安定だったと思います。
当時は、ジンジャーとブラックペッパーがお気にいりのハーブ・スパイスでした。
カルダモン、使い方は?
インドをはじめ北欧、中東、エジプトなどで広く愛用されてきたスパイスのカルダモン。
飲み物での取り入れ方を紹介します。
チャイ
ハーブ・スパイスを牛乳や紅茶などで煮込んだチャイはマサラティーともいわれます。
マサラとは、ヒンディー語で複数のハーブ・スパイスを混ぜたもののことです。
レシピ2杯分
材料)
カルダモン(ホール)2粒、クローブ(ホール)2粒、ブラックペッパー(ホール)4粒
シナモン(スティック)1本、ジンジャー(生・スライス)2枚、水100ml
紅茶(茶葉)小さじ3、牛乳200ml、砂糖大さじ2
作り方)
①カルダモン、クローブ、ペッパーは軽くつぶします。
鍋に水、スパイスを入れて火にかけます。
沸騰したら、茶葉を入れ、弱火で1分ほど煮だします。
②上の①に牛乳と砂糖を入れ、沸騰したらすぐに火を止め。に濾しを使ってカップに注ぎ入れます。公式テキスト ハーブ&ライフ検定テキスト NPO法人日本メディカル協会検定委員会監修 抜粋
ほっとしたい時、またひと息つきたい時にチャイはお勧めです。
疲れた時に元気を出すのに甘くてスパイシーなチャイがピッタリします。
私は、カレーを作る時にカルダモンを含めたハーブ・スパイスを数種類使います。
カルダモンの香りを引き出すとカレー全体の風味が増します。
カレーの作り方)
材料)
ニンニクひとかけ、生のショウガ 2切れ。カルダモン3粒、クローブ4粒、赤唐辛子1/2本、ブラックペッパー(ホール)6粒、シナモンスティック1/2本
玉ねぎ中1個
作り方)
①ニンニクと生姜は荒いみじん切りにします。
②赤唐辛子は種をとってから、輪切りにします。
③玉ねぎはスライスをしておきます。
④鍋に分量のスパイスとニンニク・生姜をいれて、油をいれて火にかけます。
⑤油が温まってくると、スパイスの香りが出てきます。
⑥香りが立ち始めたら、玉ねぎをいれてあめ色になるまで炒めます。
このやり方をすると、市販のカレールーを使っても本格的なカレーが作れます。
カルダモンは、スーパーのハーブ・スパイスコーナーで買うことができます。
どこのブランドいいかという点は、S&B、ハウス、GABA、VOX ORGANIⅭS spiceなどがあります。
ぜひ、自分好みのドライのハーブ・スパイスと出会ってみてください。
カルダモン、香りは?
実は、カルダモンはハーブ・スパイスだけではなく、は精油もあるんです。
その香りは、心地よい刺激と明るさを与えてくれます。
集中力をアップさせたい時やリラックスしたい時にお勧めです。
カルダモンは、紀元前から活用されていたと言われています。
スパイスとして食用活用のほか、チャイなどの飲料、中医学やアーユルヴェーダ伝統医学等の伝統医学では生薬(しょうやく)として広範囲で活用されていました。
紀元前4世紀にはギリシャの医師たちが活用していました。
緊張からの回復のサポートや神経系全般に強壮効果があります。どのように精油を抽出するのかといえば、水蒸気蒸留法です。
抽出部位は種子です。
主な産地は、スリランカ、北インド、ラオス、グアテマラ
主な化学成分 1.8シネオール、α‐酢酸テルピニル、酢酸リナリル、リモネン、リナロール
主な作用 去痰、催淫、循環促進、消化促進、神経強壮、鎮痙、鎮静香りを楽しむ特徴がわかるアロマ図鑑 アネルズあづさ著
歴史上でも生薬として活用されていたり、強壮作用をもつカルダモン。
その香りは、ぎゅうと硬くなったカラダやこころがふわーっと緩んでいきます。
作用としては、去痰もあれば循環促進もあり、消化促進、神経強壮もあります。
全身の循環がよくなり、消化力のサポートがあって、気持ちも強く持てる。
ちょっと元気になりたい時、前向きな気持ちになりたい時にお勧めです。
精油は単体で使うより、ブレンドするのがいいと思います。
柑橘類や呼吸器に働きかけるユーカリ、そして地に足をつけるベチバーも合うと思います。

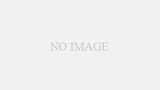
コメント