パトリス・ジュリアンさんをご存知ですか。
フランス人ですが、現在は日本に暮らしています。
日本とフランスの違いに気づき、違いを活かして暮らし方の提案をしています。
パトリス・ジュリアンさんは自分へ問いかけをした快適さを発信し続けています。
住まいも食事も暮らしも心の在り方も、すべてが自分の人生だと感じて、妥協をせずに暮らすライフスタイルをデザインしているのでしょう。
パトリス・ジュリアン
元々は、フランス大使館文化担当者として来日。
東京日仏学院の副学長や複数のレストランのオーナーシェフを務めた後にパトリス・ジュリアン・ライフスタイルデザインオフィスを設立。
パトリス・ジュリアンは、画家であり優れた料理人(コルドン・ブルー)であった母の影響を受け、幼少期から美しいもの、そして美味しいものへの深い愛情を育んできました。
教師、外交官としてのキャリアを経て、40歳のときに人生の大きな転換を決意し、「キッチンの世界へと飛び込む」ことを選びました。
日仏の違いを理解したうえでの日仏の融合がデザインとなりました。
パトリス・ジュリアンは単なるシェフではなく、「空間のクリエイター」でもあります。
彼にとって、美食とは「味覚」だけでなく、視覚、雰囲気、感覚すべてが調和するアートの一部なのです。
空間の美しさは快適さに裏打ちされています。
レストランを訪れた人は、空間をも楽しむ場所となります。
料理・インテリア・照明・音楽・サービスが快適でないといけないのです。
パトリス・ジュリアン、離婚
パトリス・ジュリアンさんのパートナーは、26歳で起業した女性でした。
フランス大使館文化担当官として来日していたフランス人のパトリス・ジュリアンと出会いました。
彼女は、それから個人創業し、フランスの生活文化を日本に紹介することに努め、28歳で法人化。料理、エッセイ本を20冊以上プロデュースし、当時売れないと言われていたフランス料理本の販売部数40万部以上を数える。
30代初めに、東京白金台に100坪を超える自社建物を取得し、一軒家でのフレンチカフェ&レストランブームの火付け役となりました。
フランス人パートナーとの関係清算後に、拡大した事業を仕切り直す。
いっぽうアロマテラピーの国際ライセンスを40歳過ぎて取得。
22年目の節目に全権委譲してレストラン経営から離れ、現在は神話の故郷であり、母方の故郷である宮崎に拠点を置く。
続いて、パトリス・ジュリアンさんはパートナーとしてのユリさんと結婚しました!
大田区洗足池のほとりの小さなレストランで行われたのんびりとした式。
新郎新婦入場で入り口をゲスト全員で見つめていると、真後ろの池を颯爽とモーターボートで投げキッスしながら横切るふたりが!
最初から最後まで笑い声のたえない、手作りの温かな結婚式でした。
当初、パトリス・ジュリアンさんとユリさんは人生のパートナーでありながら結婚という形をとっていませんでした。
それでも、現代を生きるカップルにとって素敵なメッセージが届けられるにちがいないと依頼したところ、インタビュー当日思わぬ展開に。
ユリさんは東京出身。
パトリス・ジュリアンと共に南フランス在住。
エステティックサロンを経営。
ヨーロッパ風のカフェ文化や、素朴で日常的なフランス料理を日本に紹介してきたパトリス・ジュリアンさん。
人気の煮込み鍋「ル・クルーゼ」を日本に知らしめたのも彼の功績だ。
世界を渡り歩いてライフスタイルを模索し続けてきた彼が、日本で出会った運命の女性、それがユリさんだった。
大抵のことは話し合いで解決してきた私たちだけど、パトリスさんには、どうしても承服しかねることがあったのよね。
夫:ああ、ラーメンの話ね(笑)。南フランスに住んでいたころ、村にすごくおいしいパン屋さんがあったんです。私は毎朝、焼き立てのクロワッサンやパン・オ・ショコラ(チョコレートの入ったパン)とエスプレッソが習慣なんですけど、ユリが朝からラーメン食べるんですよ!
パトリス・ジュリアン、宮津
パトリス・ジュリアンさんが暮らす宮津について、紹介します。
宮津市は、京都府北部の丹後地方に位置し、豊かな食や、歴史、文化に裏打ちされる魅力的な地域です。
近畿初の「海の京都観光圏」として認定され、近隣には日本三景「天橋立」をはじめ、風光明媚なビューポイントが多数あります。
パトリス・ジュリアンさんがこれまで手掛けたレストランには、独自の個性とコンセプトがあり、美食を超えた体験を提供することを目的としています。
それは、日本文化とフランス文化を違いをわかったうえでの融合=コラボレーションだったと思います。
カフェの場合は、店舗名に必ずル・ジャルダンがはいっています。
彼が目指した空間はジャルダン。
ジャルダンとは、フランス語で庭を意味します。
フランスにおける庭は、五感を癒す場所です。
植えられた植物たちと光が視覚を刺激し、植物の香りが鼻を刺激します。
吹き渡る風がほおをなでたり、そっと触れた葉先から植物の力を感じ取ることもできます。
植物の間でさえずる鳥の声もひびきわたるでしょう。
そう、庭は人間の五感を通して、刺激や癒しを与えてくれるのです。
パトリス・ジュリアンがつくろうとするジャルダンはある種の自然な瞑想の場、あるいは僕が“意識を集中させる”場と呼ぶもの。
僕の庭はまるで本物の庭と同じように、世界がひとりでに色を帯びる。
この魔法を見届けるには、ただ“その場所にいる”だけで、本当に“そこ”にいるだけで十分なのだ。
そして、新たなジャルダンを作る場所として京都府の宮津を選びました。
「地元の特性を尊重する」ことを大切にしており、彼が現在拠点とする「メゾン・ジュリアン宮津」では、京都府・丹後地域の食材を積極的に使用しています。
食材の地産地消を重視し、地元の生産者と連携することで、料理に深い意味とストーリーを加えています。
ワインだけでなく、日本の文化を尊重し、地元の日本酒(地酒)を厳選して提供。フランス地中海料理と丹後地方の恵みを融合させることで、他では味わえない唯一無二のダイニング体験を提供しています。
彼が作った空間は、心が安らぎ、五感と心に響く場所
リノベーションをした古民家で、リトリートとしてヒーリングも受けることができます。
忙しさのあまり、スケジュールも頭もパンパンになったら訪れて、リセットをして美味しい食事とヒーリングで充電をして日常にもどる場所ですね。
パトリス・ジュリアン、本
パトリス・ジュリアンは、フランス大使館文化担当者として来日しました。
東京日仏学院の副学長や複数のレストランのオーナーシェフを務めた後にライフスタイルデザインオフィスを設立。
外交官、教師、レストランオーナーシェフのキャリアが活かせる活動をしていますし、その活動を伝える書籍の出版も多いです。
今回は以下の3冊を取り上げます。
「きちんと暮らす」東京アスコム
「フランス料理ABⅭ 簡単・おいしい・楽しい・メニュー」文化出版局
「暮らしのZen」幻冬舎
「きちんと暮らす」は、パトリス・ジュリアンが鎌倉で一軒家を借りて暮らす中で気が付いたことを伝えています。
鎌倉に住んだ一軒家での暮らしから気づいた、フランスと日本との違いを比較しながら今ここでの暮らしの楽しみ方をまとめています。
中庭や縁側もあって、理想の住まいだと感じたそうです。
暮らしてみると日本の家屋のいいところはあっても、フランス流の良さと融合させるのには、工夫が必要だったと書いています。
大きな違いを感じたのは、空間のとらえ方だと気づいたそうです。
日本の暮らしはすべてが床の間文化であると、切り取られた住まいの美しさと良さを大事にしている。
フランスのインテリアは、部屋全体を俯瞰で見て、色の調和や家具の配置を決めていく。
その融合の過程が本の中では、結果をみることができます。
「フランス料理ABⅭ 簡単・おいしい・楽しい・メニュー」
フランス料理って、イメージとしてはハードルが高いですよね。
この本では、調理時間は30分以内で予算も2人前で約1000円、簡単に手に入る食材が使われています。
フランスの家庭で料理されているレシピがヒントとなっているカジュアルな料理やおしゃれな料理、エスニック風味も紹介されています。
スープ、野菜・サラダ、魚料理・肉料理・デザートなど
また、そのほかに食事を楽しむためのヒントが紹介されています。
料理の組合せ、献立のたて方、テーブルセッティングについて、調理器具について、ワインについて、ハーブとスパイスについて、チーズとパンについての知識もあります。
「暮らしのZen」
パトリス・ジュリアンは、zenに関する著書も手がけています。
実は、「きちんと暮らす」の中には、坊主頭になったパトリス・ジュリアンが登場します。
そして、本の中で禅の老師との出会いが書かれています。
「暮らしのZen」の中でパトリス・ジュリアンが、日常の中に「悟り」を見出す方法をAからZまで明かしていく内容です。
21世紀を迎え、パトリス・ジュリアンが感じる危機感。
人間は他の動物や植物や鉱物に比べて優位に立つものではない。
逆に人間こそがこの世に存在する他のすべてに敬意を払わなくてはならない存在なのである、と。
手のひらに握ったたった1個の石からも、自分の意識を無限大に広げることができる。
自分の息にじっと集中すると、それは外の世界と自分をつなぐものとして自然と世界との出会いへと導いていってくれる。
非常に残念ながら、パトリス・ジュリアンの著書は現在、本屋での取り扱いは少ない。
そこで、地域の図書館などで検索するのをお勧めします。
鎌倉で禅に出会い、エゴを取り去ることにも取り組んできたパトリス・ジュリアン。
暮らしの中で大切にすること、心地よさやリセットする方法かもしれません。
そして、生きていくうえで大事な食事についても味わう・楽しむことの提案をしてくれています。

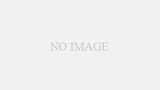
コメント