ハーブは健康に維持に役立つと聞いたことはありますか。
ハーブと言っても、何から学べばいいかと迷いますよね。
初心者向けにお勧めの人物がいます。
それが、12世紀のドイツに生まれ、修道院に入って暮らしたヒルデガルト・フォン・ビンゲンといいます。
彼女は、神学以外の学問にも精通し、医学、薬学、音楽でも著書を残しています。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン
ヒルデガルト・フォン・ビンゲンは、神聖ローマ帝国のドイツ王国、ラインラントのベルマースハイム村で、地方貴族の10番目の子どもとして生まれました。
両親が望んだ聖職者としての生活を自ら選び、ディジボーデンベルクにあるベネディクト会系男子修道院の修道女ユッタによって育てられます。
後に、ユッタは同じ敷地内に女子修道院を設立して院長となります。
ユッタが死去すると、ヒルデガルトが女子修道院の院長に就任します。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲンは40代以降から才能を開花させました。
49歳の頃には作曲も手がけ、典礼用の宗教曲を作詞作曲しました。
ヒルデガルトの名声が高くなると、ヒルデガルトの教えを求め、各地から修道女が集まるようになります。
ユッタから引き継いだ修道院が手狭になったことから、ルぺルツ近郊に新しい女子修道院を建設し、教師、著述、医者、博物学者、作曲家としての才能を発揮します。
医療活動においては、数多くのハーブを栽培して自然を広く研究し、治療のために薬草、植物などを活用する著書「フィジカ」を書きました。
10人も子どもがいれば、その中から聖職者を目指すのも不思議ではありませんが、筋金入りという気もします。
ただ、この時代は修道院は男性中心でした。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲンは幸運なことに、女性修道士によって育てられ、その才能を発揮することができました。
その活躍を知って、多くの女性が修道院を目指したのも何となくうなづけます。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン、ハーブ療法
12世紀のドイツの修道女ヒルデガルト・フォン・ビンゲンは、神学書以外に医学、薬学、音楽などの著書を多く残しています。
修道女でありながら、医学や薬学にまで幅広い知識を得ることができたのでしょうか。
当時の一般市民の生活には学問は存在しなかったのですが、修道院だけは学問と教育を手にすることができました。
そして、修道院は市民の病院の役目を果たしていました。
中世における組織的医療機関は、修道院に限られ、病人だけではなく、巡礼者や貧しい人を宿泊させ、慈善医療を提供していました。
修道女の一番の役目は病人の介護、健康管理でした。
食生活においても、修道院では高い教育水準が発揮されました。
修道士女は語学能力もあり、ラテン語やギリシャ語で書かれた料理書などを読み、多くの知識を得ていました。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲンだけではなく、病人の介護や健康管理のための食事を研究し続ける修道士女の存在があって、今日まで伝えられています。
多くの修道院の庭にはハーブ畑があります。
もちろん、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの修道院の畑でも多くの薬用植物が栽培されていました。
薬用植物としてのハーブやスパイスは、ドイツに限らず遠い外国からも取り寄せられました。
治療のための研究が重ねられ、お茶のように煎じて飲ませたり。料理に混ぜて患者に与えられていました。
修道士女たちは自給自足の生活をしていました。畑仕事に家畜の世話、パンを焼き、保存食を作る生活。
ベリー類が実るころはジャムを煮て瓶詰にしたり、チーズやソーセージなども作っていました。
修道院内では鶏や豚、イノシシなどを飼育し、養魚池には魚を泳がせ、必要な時には調理をしていました。
冬を越すための保存食として、豚などは頭から足の先まで無駄にすることはなく使われました。
食材を長く持たせる保存方法も、食材ごとに工夫と研究をしていました。肉や魚は塩漬けや燻製のして、野菜はビネガーを使ったマリネが考案されました。
果物類は砂糖と共に煮てジャムなどにしています。
保存している肉や魚類はにおいがきつくなるのでハーブを使って香りを加えていました。
風味やハーブによる健康効果まで考えて研究していました。
調理担当の修道士女たちは時間をかけて試行錯誤をしながら、新しい料理を生み出していきました。
野菜とともにじっくりと煮込んだ肉料理はまさしく修道院の料理でした。
医療を提供できる場所としての修道院が病人や巡礼者、貧しい人を介護し、健康管理を担っていたんですね。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲンは、医学、薬学の知識を得ながら重要な役割をもって活動をしていたということになります。
ハーブをとり入れていて健康管理をしているはずの修道院でしたが、中にはぜいたくな食生活をするように陥っていた修道院もありました。
荒廃しかけた修道会を立て直すために、食という分野で新しい指針をたてたのは、ビンゲンの修道院長だったヒルデガルト・フォン・ビンゲンでした。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲンが勧める果物や野菜、ハーブやスパイスには健康管理の意味が込められています。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの時代の医学は、東洋の薬草学に通じるような考え方を多く発見します。
素材の組合せやハーブの使い方など800年以上の時を経ても、現代の食卓に活かせるヒントが多数あります。
ハーブの研究では、カトリック教会の修道会ベネディクト会やそこから派生したシトー会の修道士たちが大きな功績を残しました。
一年中採れるハーブ以外は、いつでも使えるように乾燥をさせることを考え出したのも彼らです。
そのハーブ研究を食に利用したのが、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンでした。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲンが50歳を過ぎてから書き示した「フィジカ」(邦題 聖ヒルデガルトの医学と自然学)には、薬草230種、樹木63種の解説がなされています。いまだにその知恵は現代に活かされています。
ヒルデガルトのレシピに使用されるハーブ、スパイス類は、ドイツをはじめヨーロッパの薬局や自然食品店でヒルデガルトのハーブとして販売されています。
ヒルデガルトのハーブとして一部を紹介します。
ハーブ
ディル、バジル、マジョラム、ミント、オレガノ、パセリ、タイム
スパイス
フェヌグリーク、キャラウェイ、クローブ、ナツメグ、こしょう、シナモン、ガランガー、しょうが、にんにく
野菜
えんどう豆、クレソン、フェンネル、根セロリ、コールラビ、かぼちゃ、玉ねぎ、そら豆
果物
リンゴ、ベリー類、西洋梨、栗、オレンジ、レモン、プルーン、桃、ぶどう、くるみ
調味料
塩、砂糖、ひまわり油、はちみつ、ワインビネガー、ワイン、
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン、宝石療法
ヒルデガルト・フォン・ビンゲンは、女性が本を書くことや勉強を許されていない時代に初めて教皇に認められた女性で、40歳を過ぎてから、修道院長になりました。
弱者に寄り添い続けたヒルデガルト・フォン・ビンゲン。
医学や薬学、健康管理にとどまりませんでした。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの治療とは、生活習慣と食生活、そして自然と人間の調和をさせて人間本来の自然治癒力を生かそうという目的があります。
人間の調和とは、人間の4大元素(土・水・火・空気)との調和を意味します。
4大元素とは、世界のすべての物質は「土」「水」「火」「空気(風)」の4つの基本的な要素から成り立っているという古代の思想です。
この思想は紀元前5世紀頃に古代ギリシアの哲学者エンペドクレスによって提唱され、プラトンやアリストテレスといった後の哲学者たちにも受け継がれ、広く普及しました。
4大元素は、現実の物質そのものを指すのではなく、それぞれの物質を支える基盤や性質を象徴しています。
例えば、土は力強さ、水は浄化、空気(風)は活力、火は再生といった働きに対応すると考えられています。
この概念は、古代ギリシア・ローマ、イスラーム世界、そしてヨーロッパの医学や錬金術の基礎となり、占星術や心理学の分野にも影響を与えました。
ヒルデガルトは、自然と人間の調和をするために、ハーブと石(宝石)の力用い、人間本来の自然治癒力を生かそうという考えです。
それが、宝石療法です。
ヒルデガルト・フォン・ビンゲンによると、宝石は4元素(土・水・火・空気)と三位一体(神・子・精霊)の力を宿しています。
人間の魂も同じように4元素と三位一体の力をもち、髪の姿に似せてつくられています。宝石の波動は、弱ったわたしたちの体・心・魂と響き合い、中庸に戻して癒すためです。
石をもっておく、あるいはネックレスなどにして身につけることも癒しになります。
宝石療法でのいちばん簡単な方法は、宝石ウォーターです。
ガラス容器に入った水の中に水晶・アメジストをいれます。24時間、太陽の光に当たるように置けば、宝石ウォーターができあがります。普段の飲み水として、宝石ウォーターを使ってみましょう。
ヒルデガルトによると、水晶は浄化、アメジストは美肌や虫除けになります。
水晶は古くから浄化の石として使われてきました。
ヒルデガルトの宝石療法で使う一部を紹介しましょう。
エメラルド
オニキス
アクアマリン
サード二クス
ラピスラズリ
カルセドニー
ルビー
アメジスト
水晶
ただし、宝石ウォーターを作る場合、すべての宝石が使えるわけではありません。見ずに入れると有害物質が溶け出すものもありますので十分、注意してください。
弱った体や心、魂をバランスをとるための方法のひとつが宝石療法だと言えます。
アクセサリーとして、いいなあと思った宝石を身につけると、心が落ち着くことがあります。
また、気持ちに合わせて、宝石が持つ役割を調べて宝石を選ぶのも宝石療法といえるかもしれません。
12世紀に活躍したヒルデガルトが宝石療法まで記録としていたことに驚いています。
修道女として、弱った人に寄り添うことをしてきたからこそ、健康管理としての宝石療法なのかもしれません。
人がバランスを取るためには、食生活や生活習慣が基本となります。
基本を調えたうえで、宝石療法をとりいれてもよいのかもしれません。
薬草に精通し、食べ方も指導ができて、音楽や宝石を使った癒し(セラピー)も確立したヒルデガルト・フォン・ビンゲンは、今の時代でいえば、二刀流どころではなかったということですね。
私たちも、様々な仕事に趣味を楽しんでいいのだと教えてくれています。

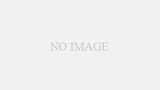
コメント